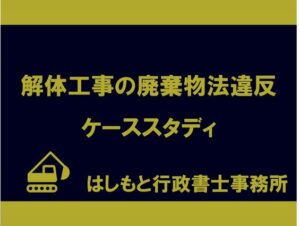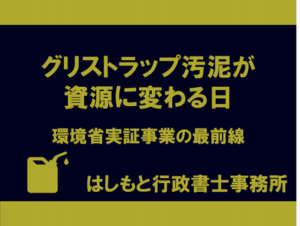解体工事業のリスク管理|廃棄物処理法など法律違反を防ぐための実務ガイド
前回の記事で解体工事における廃棄物処理法違反を解説しました。
2025年8月19日付 「解体工事の廃棄物法違反ケーススタディ|元請・下請・孫請の違反事例」
解体工事を行う際は、廃棄物処理法だけでなく、多くの法律に基づいて適正に行う必要があります。
発注者や元請け、下請けを含め、関係者全員に法的責任があるため、違反すると行政処分や罰則の対象となります。
それでは、解体工事に関係する主な法律と、実務での注意点をわかりやすく解説します。
解体工事で事業者が押さえるべき法律5選
解体工事で関係する法律は、主に以下のような法律です。
①廃棄物処理法
②建設業法
③建設リサイクル法
④大気汚染防止法
⑤道路交通法
簡単に各法律の概要を説明すると以下のとおりです。
廃棄物処理法 – 産業廃棄物収集運搬業の許可と産業廃棄物の適正処理とマニフェスト管理
建設リサイクル法 – 500万円未満の工事における解体工事業登録の取得、解体前の事前届出、分別解体
建設業法 – 500万円以上の解体工事時には建設業許可の取得、下請契約ルール
大気汚染防止法 – 解体工事前のアスベスト調査・届出・飛散防止
道路交通法 – 重機・ダンプの搬出入と道路使用許可
それでは、各法律のポイントを解説していきます。
廃棄物処理法
まずは、「廃棄物処理法」は解体工事において必ず発生する産業廃棄物に関する規制です。
廃棄物処理法は、これまでも当ブログで解説してきましたが、廃棄物の排出を抑制し、適正な処理を行うことで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。
実務上の注意点
廃棄物処理法上、建設工事における排出事業者は、「元請業者」と定義されています。(法第21条の3)
よって、元請業者が産業廃棄物を運搬する際は許可不要ですが、下請、孫請業者が運搬する際は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
産業廃棄物の処理責任は、排出事業者である「元請業者」にあります。よって、元請業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、委託契約書の作成やマニフェスト発行の責任が生じます。
・委託契約書の作成
・マニフェストの発行、保存
・産業廃棄物収集運搬業の許可の取得
違反例
- 無許可営業: 下請や孫請業者が産業廃棄物を運搬する場合、許可を取得する必要があります。
- 委託契約書の未作成: 排出事業者(解体工事の元請業者)が産業廃棄物の処理を委託する場合、事前に委託契約書を作成する必要があります。
- マニフェストの未発行、虚偽記載: 排出事業者(解体工事の元請業者)がマニフェストを交付しなかったり、虚偽の内容を記載したりする行為。
- 不法投棄: 解体工事で生じた産業廃棄物を、費用を安く抑えるために山林や他人の土地にみだりに投棄する行為。
建設リサイクル法
次に、「建設リサイクル法」は、解体工事に必ず必要な登録と届出を必要としています。
建設リサイクル法は、建設工事から生じるコンクリート、アスファルト、木材などの特定建設資材廃棄物を分別解体し、再資源化して再利用できるようにすることを目的とした法律です。一定規模以上の新築・解体工事などが対象で、工事の受注者は分別解体と再資源化が義務付けられています。また、工事の事前届出、請負契約への明記、そして適正な工事実施を確保するための解体工事業者の登録制度も定められています。
実務上の注意点
建設リサイクル法で定められた一定規模以上の解体時には、対象建設工事の着工7日前までに、発注者が都道府県知事に分別解体等の計画を届け出る必要があります。
また、解体工事業者の登録制度が規定されており、適正な解体工事の実施を確保するため、解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されています。
・解体工事実施前の事前届出
・解体工事業者の登録
・解体工事実施時の標識掲示
違反例
- 届出を怠る: 対象となる規模の解体工事について、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出をしない。
- 解体工事業登録なしでの工事: 500万円未満の解体工事であっても、「解体工事業登録」が必要です。登録なしで営業した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
建設業法
先ほどの建設リサイクル法に加え、解体工事の金額によっては、「建設業法」が関係します。
建設業法とは、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを目的として、建設業者の許可制度や工事契約に関するルールなどを定めた日本の法律です。
実務上の注意点
解体工事を行う際は、建設リサイクル法の解体工事登録が必要となりますが、工事の金額が500万円以上となる場合は、建設業の許可が必要となります。
・500万円以上の解体工事は建設工事の許可が必要
・解体工事時の標識掲示
違反例
- 無許可営業: 請負代金の合計額が500万円以上(税込)の解体工事を行う場合、建設業の許可が必要です。これに違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
- 標識の未掲示: 解体工事業者は、営業所や工事現場に標識を掲示する義務があります。これを怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
大気汚染防止法
「大気汚染防止法」では、解体工事を行う建築物のアスベストに関する規制をしています。
大気汚染防止法は、大気の汚染から国民の健康と生活環境を保全することを目的として、制定された法律です。解体工事のアスベストの他に工場や事業場などの固定発生源から排出・飛散する大気汚染物質に対して規制を設けるとともに、自動車排出ガスに対する許容限度も定めています。
実務上の注意点
令和5年10月より建築物の解体工事前に、当該建築物にアスベストが含有されていないか事前調査を行うことが大気汚染防止法において義務化されました。
さらに、令和4年4月から、次のいずれかに該当する場合は、特定建築材料の使用の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必須です!
・建築物の解体工事:作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の改造・補修工事:請負代金の合計が100万円以上
・工作物※の解体等工事:請負代金の合計が100万円以上 (※特定工作物(環境大臣が定める工作物))
また、飛散性アスベスト(レベル1、2)の工事時には、特定粉じん排出等作業届を作業開始前に提出する必要があります。その他、各自治体の条例などによって非飛散性アスベスト(レベル3)の工事着手前の届出が求められています。
違反例
- アスベスト事前調査の未実施: 解体工事を行う際、事前に建材にアスベストが含まれているか調査する義務を怠る行為です。調査をせずに解体作業を開始したとして、書類送検された事例も報告されています。
- 虚偽の調査報告: アスベストの含有を否定する虚偽の調査報告書を提出し、工事中にアスベストが飛散する事態を引き起こした事例があります。公共施設での工事でこのような違反が発覚し、受注業者が契約解除や入札停止処分を受けた例も知られています。
- 事前調査結果の報告義務違反: 一定規模以上の工事では、アスベストの事前調査結果を行政に報告する義務があります。この報告を怠る、または虚偽の報告を行うと罰則の対象となります。
- 不適切な事前調査: 有資格者ではない者が調査を行ったり、調査に不備があったりして、アスベストを見逃してしまうケースです。その結果、工事中にアスベストが飛散し、健康被害のリスクが発生します。
道路交通法
道路交通法(道交法)は、日本における道路上での危険防止、交通の安全と円滑化、および交通に起因する障害の防止を目的とした法律です。
実務上の注意点
解体工事を道路に面した場所で行う場合、道路交通法に基づき「道路使用許可」が必須となります。無許可で道路に重機や資材を置いたり、作業を行ったりすると、法律違反となり罰則の対象になります。
違反例
- 無許可での道路使用:解体工事に必要な道路使用許可を得ずに、車両の駐車、資材の仮置き、重機の積み降ろし、または作業スペースの確保などを道路上で行う行為。
まとめ
解体工事は、廃棄物処理法や建設リサイクル法など複数の法律に基づいて進める必要があります。これらの法令を遵守することは、行政処分や罰則を回避するだけでなく、取引先や発注者からの信頼を守ることにも直結します。現場ごとに「どの法律が関わるのか」を確認し、契約書や届出を正しく整備することが、安定した経営と長期的な事業継続につながります。