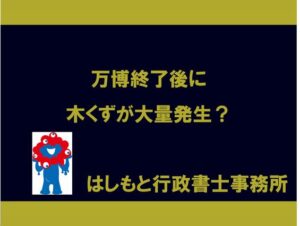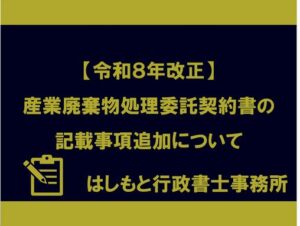適正な最終処分とは?
産業廃棄物の最終目的地は?と聞かれるとまず最初に「埋立」や「最終処分」という言葉が浮かぶのではないでしょうか。
産業廃棄物の中でも、特にリサイクルできない破砕後の残さや焼却残さである燃え殻やばいじん、アスベスト廃棄物などは埋立処分するしかないものがほとんどです。
そんな最終処分場である埋立地の話題が報道されていました。
| 広島市安佐南区の不適切な盛り土の上に広がる産廃処分場に、ゴミが野積みされています。住民らで作る団体は、28日、広島市に対し、事業者に運用改善を指導するよう求めました。 【出典】2024年4月29日 中国放送 「「不適切な盛土」の上部に広がる産廃処分場で膨大なゴミが野積み状態 市民の会が指導求めて申し入れ 広島」 |


一見すると不法投棄現場ではないかと思うほど、廃棄物が露出しているため悪質な埋立であることはわかります。実際、私が見てきた最終処分場もここまで酷い状況の施設はありませんでした。
それでは、最終処分場が廃棄物処理法のどのような基準において規制されているか確認してみます。
産業廃棄物処理業者に適用される基準は2種類あります。まず1つ目は「産業廃棄物処理基準」です。さらに、最終処分場などの産業廃棄物処理施設には「施設基準」が適用されます。
今回は、「施設基準」に関して確認していきましょう。施設の許可基準は次の条文に記載があります。
(許可の基準等)
廃棄物処理法第15条の2
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
(以下略)(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
廃棄物処理法第15条の2の3
産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
施設の基準には「構造基準」と「維持管理基準」の2種類があります。
最終処分場の具体的な技術上の基準は、次に示す「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に記載があります。今回は、記事にあった安定型処分場に関して確認します。
(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
第2条 法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
(中略)
三 令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、第一条第一項第四号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第2号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
ロ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。
ハ 埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。
(中略)
2 法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(中略)
二 安定型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第7号、第19号及び第20号の規定の例によるほか、次によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)」及び「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。
イ 前項第3号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。
ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
(2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
ニ ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ホ 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。
(1) 地下水等検査項目 一年に一回以上
(2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上
ヘ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
(1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき。
(2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。
ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね50センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。
チ トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
文字ばかりなのでわかりにくいと思いますので、簡単に各基準を抽出すると、
【構造基準】
・地滑防止工
・沈下防止工
・立札
・擁壁等
・囲い
・雨水等の排出設備
・浸透水の採取設備
【維持管理基準】
・飛散防止設備
・消火設備
・展開検査設備
・周縁地下水採取設備
これらが施設を設置すると求められる基準ですが、記事にあった廃棄物の露出は何が問題かというと維持管理基準にある飛散防止の対策に係る部分です。
一 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
廃棄物が露出していると埋立地からの廃棄物の飛散流出や悪臭の発散を防止できないため、維持管理基準において一定以上の廃棄物を埋め立てた後に覆土をする「中間覆土」を行うのが一般的です。
法律において明確に「中間覆土」を基準として設けているわけではありませんが、維持管理基準として飛散流出や悪臭対策を講じることの記載を行政側に求められることになります。
また、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領」において覆土について以下のように記載があります。
【指針に記載された「覆土」】
| ⑴ | 埋立ごみは放置することなく、すみやかに覆土を行わなければならない。厚さは、ごみの種類、覆土材料の種類によって選定する。 |
| ⑵ | ガスの拡散防止、火災予防及び必要に応じてごみの収集運搬者の通行のため、所定の区域に対して覆土を行わなければならない。 |
| ⑶ | 埋立地の最上層には、最終の覆土を行わなければならない。厚さは、跡地利用計画等を勘案して決定しなければならない。 |
| ⑷ | 覆土材の種類、量の確保、経済性 |
| ⑸ | ごみ層の表面を覆い、締め固め、所定の厚さと勾配 |
よって、今回のように廃棄物が埋め立て地上に露出した状態は、埋立地から周辺への廃棄物の飛散流出や悪臭の発散を引き起こすと考えられるため、維持管理基準上の違反となることでしょう。維持管理基準の違反は直罰ではありませんが、違反を行政側が認知した場合、処理施設の改善命令(法第15条の2の7)が発出されたのちに罰則(法第26条第2号)が科せられることになります。
今回のようなケースでは、管轄の行政機関は速やかに事業場に立入検査を行い、報告徴収等を行ったうえで改善命令を発出する必要があります。現在確認できる指導状況は、2回の口頭指導と1回の文書指導による、改善報告書の提出を求めているようです。(2025年5月11日 中國新聞 「広島市安佐南区に大量の産廃野積み 市が東京の業者に文書指導」)
場所が不適切な盛土の上にあるということで、1日も早い行政の速やかな対応が望まれます。
関連記事
受付時間:9:00〜20:00 [土日祝除く]
24時間受付中