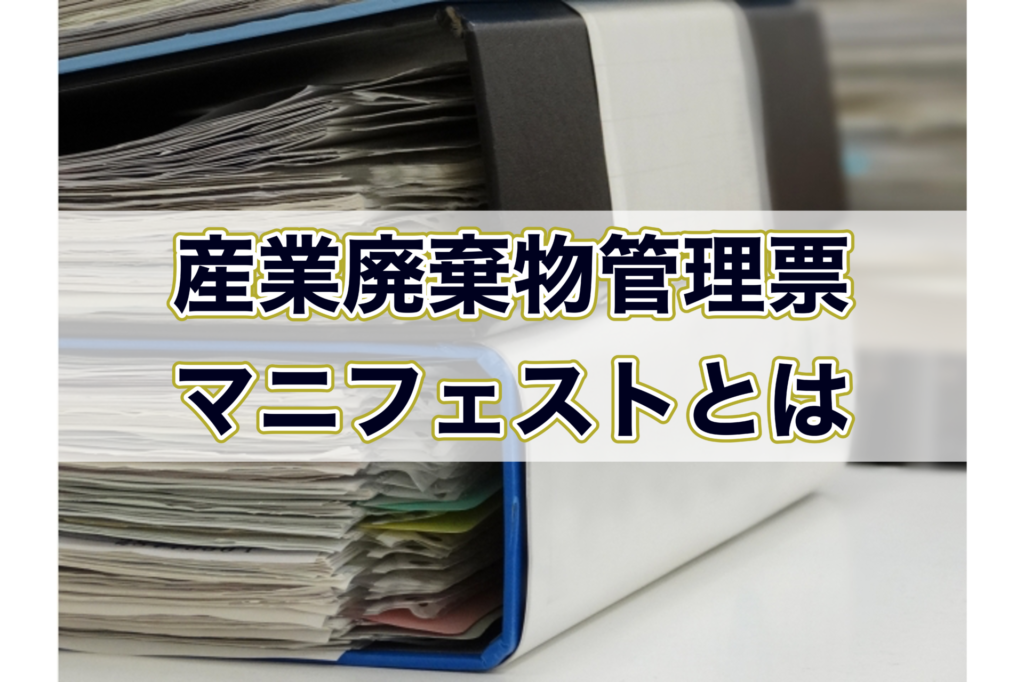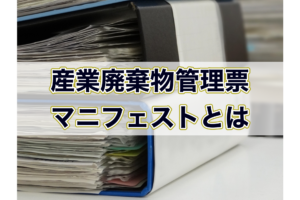産業廃棄物の処理を委託する仕組み
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、 産業廃棄物の処理を委託する仕組み についてお伝えします。
産業廃棄物を排出した場合、自分で処理できないので、基本的には専門の業者に依頼すると思います。
その依頼する際にも、廃棄物処理法ではしっかりとしたルールが決められています。
さて、どのようなルールがあるのでしょうか。
関連記事
排出事業者の責任とは
廃棄物処理法上、自ら排出した産業廃棄物は自分で適正に処理しなければなりません。(法3条)
ただし、自社で処理施設を持ち合わせている事業者はほとんどいません。
そこで、専門の事業者である収集運搬業者や処分業者に処理を依頼することになります。
排出事業者は、委託する事業者と委託契約を結ぶ必要があります。
それでは、委託契約の仕組みについて詳しく確認しましょう。
委託契約の主体
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、どのような仕組みになっているのでしょうか。
それは、排出事業者が、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ委託契約を結ぶ必要があります。
よく勘違いされるのは、
「運搬だけ委託すれば運搬業者が知り合いの処分先まで持って行ってくれるんでしょ」
と思っている人がいることです。
廃棄物処理法における委託契約の主体は、「排出事業者」です。
排出事業者が自ら「収集運搬業者」と「処分業者」を選んで委託契約を結ばなければなりません。
不適正処理の責任は排出事業者にも
さきほどお伝えしたように産廃の処理を委託する際は、排出事業者が主体です。
産廃の処理を委託してもちゃんと処理されなかった場合、責任を問われることがあります。
最悪の場合、適正に処理されなかった産廃を排出事業者が自ら引き取り、処理する必要が生じたり、
行政が代執行した費用を支払う必要が生じてきます。
過去にあった処理業者の不適正処理案件として有名なのが、食品廃棄物の不正転売事案です。
詳細な内容については、環境省のサイトから確認できます。
このように、産廃の処理を委託する際は、適正に処理が行われるように注意する必要があります。
適正処理するために
排出事業者として責任を問われることもある産廃の処理の委託。
適正に処理するためにどのようなことに注意すればいいのでしょうか。
委託する場合主な注意点を書いておきます。
- 処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいるか
- マニフェストを適切に交付・保存しているか
- 返送されたマニフェストの内容は適切か
- 委託する業者が許可を持っているか(許可期限が切れていないかを含め)
- 著しく安い処理料金で業者に委託していないか
- 定期的に委託先の処分場を確認する。
廃棄物処理法では、排出事業者の現地確認を努力義務としています。
廃棄物処理法第 12 条第 7 項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
定期的な処分先の確認は、適正処理を確認する上で重要なことです。
産廃の処理を委託する場合は、委託する業者の許可証や料金などが適正かしっかり見極めるようにしましょう。
また、通常の許可基準より厳しい基準に適合した優良な事業者をこちらで検索することができます。
処理を委託する際の参考にしていただければと思います。
まとめ
今回は、産業廃棄物の処理を委託する仕組みについて説明しました。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、事前のチェックが重要です。
不適正処理に加担しないよう、事業者選びには細心の注意を払ってください。
廃棄物処理法の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。